
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の年間死者数は「戦後最多」を更新し続けており、2040年前後に約168万人のピークを迎えるという。
「超高齢化社会」の次にやってくる「多死社会」を、私たちはどのようにとらえればよいのだろうか?
人生の最後を支えるプロフェッショナルたちと一緒に、その答えを探って行こう。
「人生会議」という言葉をご存知だろうか?
炎上ニュースにくわしい人なら、お笑い芸人の小籔千豊さんが起用された厚労省の啓発ポスターのビジュアルがすぐに思い浮かぶだろう。
鼻にチューブを挿した小籔さんが、もの言えぬ人として病院のベッドに横たわり、家族に意思を伝えておかなかったことを後悔するというその内容が「患者や遺族を傷つける」として患者団体らの抗議につながり、わずか1日でポスターの掲載を取りやめることになった。
人生会議は、超高齢化に向かっている日本社会に必要なものには違いないが、どのように捉えれば正しく運用できるのだろうか?
今回は、そんな問題を川崎市立井田病院・緩和ケア内科の西智弘医師と一緒に考えてみたい。

──厚労省が作った啓発ポスターは、なぜ炎上したのでしょう?
人生会議、すなわち「自分が望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療者、ケアチームらと繰り返し話し合い、共有する取り組みであるACP(アドバンス・ケア・プランニング)」は、病気になってから行うだけでなく、健常なときから日常の中で家族や医療者の間で繰り返し行うものです。ですから、死の恐怖だけをビジュアル化すること自体、本来の主旨から離れてしまっているんですね。
「呼吸が止まったときに人工呼吸器をつけるか」とか、「食事をとれなかったら胃ろうをつけるか」とか、「病気が進んで判断できなくなったとき、誰に判断をゆだねるか」といったことを事前に書き留めておくことをAD(アドバンス・ディテクティブ)といいます。
エンディング・ノートとか、リビング・ウィルと呼ばれるものも、基本的には同じものです。でも、それを作ることが人生会議の目的ではないわけです。
意思はそのときの状況によって変わっていくものですから、家族や医療者と繰り返し対話をして価値観を共有していく人生会議=ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の取り組みが推奨されているんですね。

──確かに健常なときに「どんな風に死にたいか?」などと問われても、なかなか答えるのが難しいですよね。
僕自身、その難しさを実感することが多いです。
──西先生の著書『がんと共に生きた人が緩和ケア医に伝えた10の言葉』(PHP研究所)にも、その難しさ語ったエピソードが書かれていますね。
では、本に書いたことの中から一例を挙げましょう。
その方は、大学病院で膵臓がんの治療と並行して、当院で緩和ケア外来に通っていた78歳の男性です。仮にカトウさんとしておきましょう。ある日、診察室にカトウさんの娘さんが同行してきたことがありました。
いつもは日ごろの生活のことや他愛もない世間話をするだけなんですが、娘さんもいるので今後のことを話してみようと提案したんです。人工呼吸器とか、胃ろうなどの具体的な選択の意思についてです。
カトウさんは、「ずっとこういう話をしたいと思っていました」と喜んで帰られたんですが、話の間、娘さんがあまり会話に加わることがなかったのが気がかりでした。
──何が気がかりだったのですか?
そのときは僕の中でもはっきりしていませんでしたが、その後、病状が進み、入院となったとき、カトウさんが「家に帰りたい。自宅で最期を迎えたい」とおっしゃられたときに判明しました。
退院や自宅での訪問診療の手続きなどをするため、娘さんに病院に来てもらい、話をすることになったんです。「お父さんは最期を自宅で過ごしたいとおっしゃっています」と伝えると、娘さんはかなり激しい口調でカトウさんと僕が交わした人工呼吸器や胃ろうの話を聞いているときの不快感を指摘し、「本人は、まだ生きたいと思っているはずです。治療を続けてください」と訴えられたんです。
──娘さんが会話に加わらなかったのは、お父さんの死のことを話すこと自体が苦痛だったわけですね?
そのことに気づけなかったことを反省しましたね。そこで、「お父さんにとって何が一番いいことなのか、一緒に考えましょう」と提案し、その後、父娘でしっかりと話し合ってもらうことで退院を納得してもらいました。
──自分の死をイメージするだけでなく、それを家族で共有するのもむずかしいことなんですね。
ですから、このような本人の意志を確認することは、「人生会議」と気負わずにやることも重要です。健常なときから日常生活の気楽な雰囲気の中で、家族それぞれの想いや価値観を共有し、理解していくことが大事なんです。

──本人の意志を確認しようとするとき、家族だけで本音を引き出すのは難しいのではないでしょうか。「専門家に入ってもらいたい」という人は少なくないと思います。川崎市立井田病院内にも「ACP外来」というものがあってもいいと思いますが、いかがですか?
いや、それは難しいでしょう。先ほどのカトウさんのように、何度か通院されていて、その人となりを知っている人に頼まれるケースならば充分にあり得ますが、「初めまして」で対面する人に対して、「人生の最期はどんな風に過ごしたいですか?」なんて話はできません。
──おそらく今の話は、西先生が2017年4月に設立した、一般社団法人プラスケアの活動と関係があるのでは?
大いにありますね。最初は診察室から外に出ることを目的に、病院内の空いているスペースを使って「がんサロン」を始めたんです。こちらも診察服ではなく私服で、お茶を飲みながら、病気について悩んでいることなどを話してもらいました。
すると、診察室では決して出ることのなかった本音が聞けたりして、手応えを感じたんです。病院の中の「医師」相手に話すのと、外部の「相談相手」に話すのとでは、話しやすさが違ってくるんですよね。そこで、本格的に病院の外に出て、「暮らしの保健室」という地域交流の場を設けたんです。
──診察室では聞けなかった患者さんの本音というと、どんなものですか?
例えば、「家族と過ごす時間をできるだけ長くしたいと抗がん剤治療を始めたけど、やはり辛くてやめたい。だけど、治療の効果を期待している家族にそのことを言い出せない」とかね。
暮らしの保健室は、町中のカフェを利用したスペースなんですが、そこにはコミュニティ・ナースといって、病院やクリニックではない、地域で働くナースが常駐しています。
それから、鍼灸師による「お灸セルフケア教室」とか、オシャレをすることで心を癒す「化粧外来」といった集まりを定期的に開いていて、病気のこと、人生のこと、家族のことなどを気軽に相談できる機会を設けているんです。

──社会が超高齢化し、医療費の増大が問題視されていますが、国はそれを受けて入院医療ではなく、外来での診療や在宅訪問での医療提供を行うことを推進しています。特に近年は、「在宅での看取り」に注目が集まっています。西先生はそれについて、どう考えていますか?
人が最もくつろげる場所は病院のベッドよりも自宅でしょうから、「最期は自宅で死を迎えたい」というのは自然な願いだと思います。
ただ、「在宅死=善」で、「その他=悪」という風に概念が固定されてしまうことには賛成できません。
病院で亡くなることについては、不必要な延命治療を受けて、生きる屍のようになった人が多くいたころに悪いイメージがついてしまいましたが、その反面、近年の多くの病院では、苦痛を最大限に抑えながら、死を安らかに過ごすことができる設備や医療体制が整いつつあります。
介護施設にしても、昔は「自分の親を姥捨て山に入れるのか」と非難する目があったのも事実ですが、最近ではスタッフや設備の整備が進んで、ずいぶんとイメージがよくなりました。ひとり暮らしの自宅で亡くなるよりも、施設内で形成されたコミュニティの中で最期を迎えたいと思う人が多くいると言われても不思議ではありません。
──にもかかわらず、「在宅死=善」という声が高まっているのはなぜでしょう?
おそらく、本当は自宅で最期を迎えたいのに、介護力不足や在宅資源が未整備だったことによって病院で過ごさざるを得ない方がかつては大勢いて、最近になってその問題が解消されてきたからだと思います。
ただ、大事なのは死を前にした人に対して、社会が「あなたはどこで最期を迎えたいですか?」と問いかけることができるということ。そして、自宅でも、病院でも、介護施設でも、その人の意思を尊重してどちらも選べるということです。

──非常に納得のできるお話です。では、最後にお聞きします。西先生自身は、どのような最期を迎えたいと思っていますか?
まだ30代の後半ですので、具体的に自分の最期をイメージするのは難しいですね。できることなら、そのときの社会が「どんな最期を迎えるか」を選べる社会であって欲しいですね。
今も未来も変わらない願望があるとすれば、それは、家族と過ごしたいということでしょうか。妻はもちろんですが、特に子どもとは同じ時間を過ごしたいと思っています。自分がどのように死んでいったかを見せるというのは、親にとって最後の教育ですからね。
もちろん、苦しんで死んでいく姿を見せるのも、ある意味で深い教育になるでしょうけれども、できれば静かに安らかに、満足して死んでいく姿を見せたいですね。そんな自分自身の願いを実現できる社会作りに貢献していくことが、緩和ケア医としての僕のこれからの使命だと思っています。


「ボブ内藤」名義でも活動。編集プロダクション方南ぐみを経て2009年にフリーに。1990年より25年間で1500を超える企業を取材。また、財界人、有名人、芸能人にも連載を通じて2000人強にインタビューしている。著書に『ニッポンを発信する外国人たち』『はじめての輪行』(ともに洋泉社)などがある。
内藤 孝宏さんの記事をもっとみる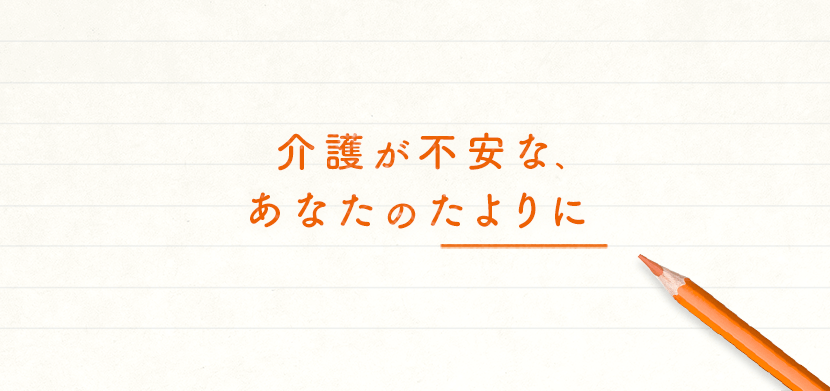
tayoriniをフォローして
最新情報を受け取る