だれかの死を惜しみ、悲しむまわりの人々の気持ちは当然のものであり、まわりの人たちにはそうする権利がある。
だが、だれかの人生について語り直されるのを見るとき、一生の物語の中で「終わり方」が大き過ぎる位置を占める語りは好きになれなかった。
例えば寂しい老後だった、誰も看取る人がいなかった、苦痛の大きい死に方だった……。そんなことでそれまでが全部間違っていたとか、悲しい話みたいになってしまうのはおかしくないだろうか。イソップ寓話に出てくるキリギリスは冬に食べるものがなくて凍えて死んだから、アリよりも悲しい人生なのだろうか?
死を悲しむことはあっても、人生そのものが悲しいものであったかのように改変されてしまうのは、どうしても嫌だと思った。
わたしは独身で子供もいないので、いわゆる孤独死を迎える可能性が高い。まわりに迷惑をかけないためにも、いつか死んだとき早めに発見される方策も考えておかないといけないだろう。
ただ、そうした現実的な算段より前に、やってみたいことがあった。もし自分のことを偲んでくれる人がいるならば、その人には楽しかったことばかり思い出してほしい。例えるなら、キリギリスにも歌って踊った夏があったことを否応なく思い出すような仕掛けをしてみたい。
そんな思いから、わたしは「西アフリカで自分のための棺桶をつくる」という素っ頓狂(すっとんきょう)な行為に出たのだった。

西アフリカ・ガーナの一部の地域に、装飾棺桶という風習がある。亡くなった人にゆかりの深いモチーフで木製の棺桶をつくり、盛大に弔うのだ。棺桶のモチーフはエビやカカオの実、携帯電話から飛行機など多岐にわたり、色づかいも派手で愉快なものが多い。
明るい造形に興味を惹かれ、装飾棺桶について調べていくうちに、わたしは自分の死に風穴を空けるためにこの棺桶を使えないかと考えた。たとえどんな終わり方になろうとも、この棺桶が鎮座していれば見た人がちょっと笑ってしまうようなものをつくってみたい。
そこでわたしはガーナに行って、棺桶工房で自分用の棺桶をオーダーして制作工程も見学させてもらい、完成したものを日本になんとか持って帰ってきた(その顛末は、旅と死をテーマにしたエッセイ『メメントモリ・ジャーニー』(亜紀書房)に詳しく書いている)。
わたしは今、東京の会社から中国・上海の子会社に出向して働いているのだが、長くても数年の一時的なものなので東京の部屋はそのままに残してある。棺桶はローテーブルとして部屋の中央に鎮座している。月に一回、留守宅清掃の人が来て、不在中に届いた郵便物や清掃レポートを棺桶の上に整頓して載せていく。契約のときに「変わったテーブルですね」と言っていたが、まさか棺桶だとは思ったこともないだろう。
ガーナにおける装飾棺桶は、本来わたしのような一介の会社員ではなく、社会的に地位のある人の遺族が故人を偲び讃えてつくるもの。故人が生前、モチーフに口を出すこともないようだ。陽気な装飾棺桶と死への対抗心を結びつけたのは、わたし自身の勝手な思い入れである。
自分は死のみじめさに風穴を空ける装置を持っているから、いつどこで死を迎えることになったとしても大丈夫なのだと思いたかった。

しかし、自分の命が終わり得るものだと、すごく切実に感じていたわけではない。
数年前、年上の知人が亡くなった。彼女はまだ40代で、突然すぎる訃報に感覚が麻痺したまま、都内の斎場でのお別れ会に向かった。
会は内々のものだったが、友人や仕事仲間を通じて連絡を受けた人たちが集まっていた。わたしは彼女とネットを通じて交友していたが頻繁に会う仲ではなかったし、つながりの濃さの順番からいって自分がここに来てよかったのだろうか、と不安になった。彼女は魅力があって人気者だった一方で、限られた人しか内面に立ち入れない印象があって、わたしはなんとなく彼女との関係のバランスをこちらの片思いだと考えていた。
斎場でどきっとしたことがあった。スタッフに案内されてロビーからお別れ会の部屋に向かう途中で、炉で焼かれたお骨がストレッチャーに乗ってガラガラと出てきたのだ。わたしは「お別れ前にもう焼いてしまったの?!」と、内心とんでもなく動揺した。
結論からいうと、それは別の方のお骨だった。他の人のお骨を目にしてしまうことが葬祭場でどれくらい普通のことなのか、わたしにはよく分からない(以前アルバイトしていた葬祭場は、焼き場はまったく別の場所にあった)が、葬儀の件数も多い東京の葬祭場ならありえることなのかもしれない。
わたしは誰かにそれを言うわけにもいかず、ひとりで動揺を鎮めていたが、彼女がもし横にいたら「メレ子がビビってやんのーーー!!!」と大爆笑したのではないか、とふと思った。少なくともわたしのイメージの中では、彼女は気遣いの人でもあると同時に、大胆で不謹慎なジョークが好きな人だった。想像上の彼女が腰を折って大笑いしている横で、わたしはもうこのイメージを確かめることも修正することもできない。
亡くなった彼女は、一度わたしの部屋を訪ねてくれたことがある。わたしの棺桶はいろいろあってポテトチップスをモチーフにしているのだが、彼女は棺桶と部屋が完成したお祝いにポテトチップスを9袋くらい抱えてきて「ポテトチップス収納庫にしようよ」と棺桶にポテチを詰めていた。優雅なロングコートを羽織って、まるで物資を手に戦地を慰問しに来た映画女優みたいだった。
はしゃいでわたしの棺桶に入ってみたりしていたのに、まさかそのあとしばらくして、彼女の方がいなくなってしまうとは。

死に風穴を空けたいという欲望もそのために棺桶をつくったことも、人がいきなり亡くなってしまうことの前にはあまりにも無力だったと感じ、わたしは最近まで死についてあらためて考えることを避けていた。上海への赴任が決まり、渡航してからしばらくは生活や仕事に必死だったというのも大きい。
生まれてはじめて外国で暮らしてみて、一年半ほどたつ。正直いって、これまで感じたことのない規模のさびしさを感じている。ちょっと慣れてきたと思っては、その倍落ちこむようなことの繰り返し。そこそこ孤独に強い方だと思っていた自己評価がひっくり返り「今までほんとうに周りに恵まれていたんだな」と感心してしまう。
棺桶はわたしにとって、ただのお守りにすぎない。不安を消すために必要なものではあったが、人生を変えてくれるようなものではない。自分のさびしさと向き合えるのは自分だけ、状況を変えられるのは自分の行動だけだ。
そう気づいてから、自分が死ぬまでの間で、どこでどのように暮らし、どのように人とのつながりをつくり、どのように大事にしていきたいのかを考えるようになった。
わたしはもともと人づきあいへの苦手意識が強く、友人も多い方ではなかった。
転機となったのは、生きもの好きのコミュニティとの出会いだ。旅先で変わった虫を見つけた喜びをブログに書いたことが、虫に関する仕事の依頼につながったのだ。そこで会った人たちは、とにかく虫や生きものが好きで、好奇心や探究欲や収集欲に人生を捧げていて、まぶしくて目がつぶれそうだった。
人間以外のものへの興味が先にあり、世間的な社交への興味が薄い人が多かったため、自己紹介をほとんどしなくても会話が成り立つ。ここは風通しがいい、と思えた。彼・彼女らと一緒に生きものを見ていると、会話がなくても気まずくない。それでいて、向き合ってお茶やお酒を飲むより相手のことが分かる気がするのが不思議だった。
ただ情熱を持つ人たちに混ぜてもらっても、自分自身の中に燃料があるわけではない。そんなわたしが、コミュニティへの自分なりの関わり方として見つけたのは、「場所をつくる人」という立場だった。

2012年から、「昆虫大学」という虫や生きものをテーマにしたイベントを隔年で主催している。研究者やクリエーターが集まり、展示や物販、講演を行う場所で、わたしは「学長」を名乗っている。規模が大きくなるにつれて協力者が増えているが、出展者はわたしの最終責任で決めることになっている。イベントはわたしの「紹介したい欲求」の発露だからだ。
どんな場所でも自然と足りない役割を見つけて役に立ったり、鋭い意見を述べて存在感を示すことができる人もいるが、それが苦手ならば、自分が居心地のいい場所をつくってしまうのも手かもしれない。やりたいことと最初に手を挙げる勇気さえあれば、みんな「うちのトップはポンコツだねえ」と言いながらもサポートしてくれるものだし、頼るのは悪いことではない。
2018年秋に開催した4回目の昆虫大学は、中国から準備に関わることになりこれまで以上に大変だったが、2日間で2千人以上の来場者を迎えることができた。イベントを一緒につくるという立場で人と関わることで、友人やそれにとどまらない結びつきが増えたのも、自分にとっては良かったと思う。本名も電話番号も知らない人が少なくないし、合わないと感じればお互いにフェードアウトすることもあるが、もろい関係だとは思わない。
昆虫大学は基本的に大人をターゲットにしたイベントだが、子供たちもたくさん来てくれる。最近は、家族連れで来られる姿も目立つようになった。
先日、小さい娘さんといっしょに遠方から来てくれたお母さんから昆虫大学の感想メールをいただいた。娘さんは虫好きの女の子ということで学校では変わった子扱いされることもあるが、いろんな出展者に虫のことをたくさん教えてもらい、楽しそうに振る舞っている姿を見て、この場所は娘にとってホームなんだと思えた——という内容で、メールを読んで泣いてしまった。
完全に私利私欲のためにつくった場所だが、その居場所で心底くつろいでくれる人がいることはやっぱりうれしい。大人になって別のものに興味が移っても、世の中には意外と多種多様な居場所があること、なくても意外とつくれたりすることを頭の片隅で覚えてくれていたらいいなと思う。
「自分が知った人たちの魅力を、自分の文章や場を通じて、まだ知らない人たちに紹介したい」と言葉にすると、自分が思っていたよりずっと人間好きであったことに今更のように気づく。
自分と他人、他人と他人がつながれる場所をつくることが、今のわたしにとっては、よりよく生きることにいちばん近い。つながりから芽生えたものが誰かの中に根を下ろすことがあれば、わたし自身のことは忘れてもらってもいい。そう思うことで、いつか死ぬのが少し怖くなくなる……とまでは言い過ぎかもしれないが、そんな境地を目指したい。
今のわたしにとって「いつか訪れる死に備える」ということはつまり、「生をより良いものにする」ことなんだと感じた。そのために、大事にしたいと思えるような人とのつながりをこれからも増やしていきたいし、そのための場をもっとつくっていきたい。
ここに書いてきたことは、多くの人に参考にしてもらえるようなものではないかもしれない。けれど、どんな人たちが好きか、その人たちとどう関わるかを自分なりに時間をかけて見つけたことが、自分が生きるのを少しずつ楽にしてくれたことは伝えたい。
まだ何も具体的になっていないのだが、帰国したら数人の友人たちとのシェアハウスかワークスペースをつくれないかなと夢見ている。
家庭とも仕事とも違う、自分が自分でいられる場所を、もっと生活に近づけてみたい。風通しの良い関係と同居生活はいかにも衝突しそうだし、一過性のイベントよりずっと大きな苦労があるに違いないが、挑戦してみる価値はあるんじゃないかと思う。
棺桶も居場所づくりも、わたしにとってはキリギリスのような夏をつくる試みだ。好きなもの、できることに気づくまでが遅く、長い間ぼんやりと生きてきたけれど、ここにきて少しずつ、自分の人生が自分にとってなじむものになってきた。30代半ばにしてやっと、キリギリス見習いといった感がある。
ここからは、今の自分からはみ出し過ぎない範囲でジャブを打ち、自分にとっての「夏」を一日ずつ建設していく。それこそが、わたしの人生への逆襲なのだ。

1983年、大分県別府市生まれ。平日は会社員として勤務。2012年から、昆虫研究者やアーティストが集う新感覚昆虫イベント「昆虫大学」の企画・運営を手がける。著書に『メレンゲが腐るほど旅したい メレ子の日本おでかけ日記』(スペースシャワーネットワーク)、『ときめき昆虫学』(イースト・プレス)、『メメントモリ・ジャーニー』(亜紀書房)がある。
メレ山メレ子さんの記事をもっとみる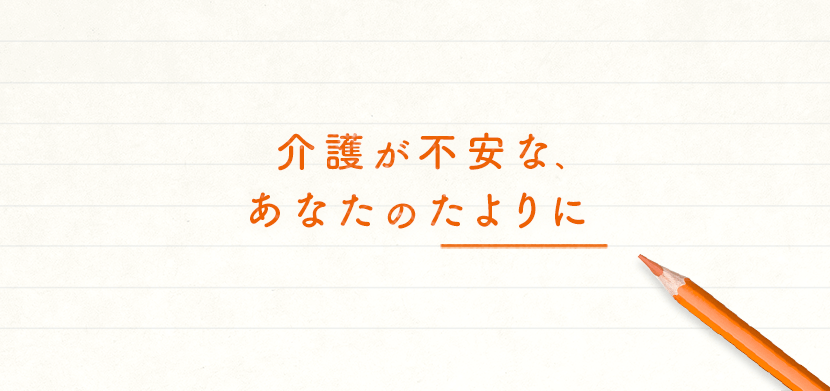
tayoriniをフォローして
最新情報を受け取る